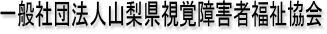山視協だより 令和3年10月号
第94号 令和3年 10月15日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
| 巻頭言 | |
|---|---|
| 銀行協会への要望に関する報告第2弾 | ・・・・・1 |
| 今後の予定 | |
| 職業部講演会開催のご案内 | ・・・・・4 |
| 支部だより | |
| 富士河口湖支部 | ・・・・・4 |
| 事務局よりお知らせ | |
| 甲府市から要望の回答がありました。 | ・・・・・5 |
| バリアフリー演劇 ヘレン・ケラー〜ひびき合うものたち | ・・・・・5 |
| 第2回視覚障害者リモート将棋大会のお知らせ | ・・・・・5 |
| マイナンバー制度の広報用資料について | ・・・・・5 |
| 編集後記 | ・・・・・6 |
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
巻頭言
銀行協会への要望に関する報告第2弾
先頭に戻る
目次へ
会長 堀口俊二
さわやかな秋晴れが続く好季節、電車にでも乗ってちょっと遠出がしてみたくなるようなこの頃です。まだまだ先行き不安なコロナですが、そろそろ静かになってほしいですね。
さて、標題の件については、7月号でも触れましたが、今月1日に行った2回目の話し合いで、銀行協会より正式な調査結果をいただきましたのでここに報告します。
調査対象は銀行協会に属する山梨中央銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、都留信用組合の9金融機関です。これに含まれていないゆうちょ銀行については、独自の調査を検討する必要があると思われます。
- 1 代筆についてはすべての金融機関で可能となっているが、窓口担当者への周知が不充分なことが懸念されるので、再度対応の徹底をはかりたい。また、具体的な対応のし方は金融機関によって異なるので、事前の問い合わせが必要。
2 ATMについては、県内544台中540台が音声ガイド対応。
3 入口からATMまでの誘導ブロックは156店舗中62店舗(39.7%)で設置。
4 入口の音声案内装置は1店舗及び店舗外ATM2箇所のみ設置。
5 点字による預金取引明細表は9金融機関中4機関(44.4%)で対応。
6 テレフォンバンクサービスは9金融機関中6機関(66.6%)で対応。
7 インターネットバンキングの音声認証対応は9金融機関中2機関。
この結果からまずわかったことは、私たちにとって最も重要とも言える代筆が、すべての金融機関で対応となっていることです。具体的な対応のしかたは各金融機関で異なるようですが、お願いする際には、是非この結果を踏まえて窓口でお話いただければと思います。音声ガイド付きATMの設置率の高さも予想以上でした。前回にも書きましたが、視覚障がい者が単独でお金の出し入れができる装置であり、会としても活用の促進をはかっていく必要がありそうです。ただ、入口からATMまでの誘導ブロックの設置率が低いので、設置要望を続けていきたいと考えます。
次に、テレフォンバンクサービスが9機関中6機関で行われているというのも朗報です。私も利用者の一人ですが、居ながらにして振り込みや残高確認ができるというのは視覚障がい者には大変ありがたいサービスです。まだ利用されていない方には是非お試しいただければと思います。
また、点字による預金取引明細表も9機関中4機関で対応となっています。私はこのサービスも利用していますが、通帳の残高はもちろん年金の振込額、電気料やガス料の支払額など、入金・出金の詳細がわかるのでこれまた大変便利です。点字使用者にはおすすめのサービスです。
以上、銀行協会からいただいた調査結果について述べてきましたが、協会の立場として残念ながら具体的な金融機関名は公表できないとのことで、サービス利用に当たっては各金融機関に問い合わせてほしいとのことでした。それでも、色々な対応がなされていることがわかったのは大きな収穫です。今後も皆さんと情報を共有しながら、視覚障がい者の金銭管理上のバリア解消に向け運動を進めましょう。
今後の予定
職業部講演会開催のご案内
先頭に戻る
目次へ
部長 酒井弘光
10月に入り、朝晩の風はめっきり秋らしくなってきました。また、新型コロナウイルス感染症の第5波もどうやらすぎさり、加えてワクチン接種もすすみ、ほんの少しではありますが、安心材料が増えてきています。まだまだ新たな波の襲来も予想されており、気の抜けない日々が続きます。
そんな中ではありますが、職業部では昨年実施できなかった職業部講演会を計画しております。内容につきましても昨年度予定していました内容で実施したいと考えております。なお、開催方法や開催会場などにつきましては、コロナ感染状況をみながら決定していきたいと考えております。詳細につきましては来月号にてご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
- 日時:12月12日(日) 10時から
会場:未定
演題:「バーチャル工房と障碍者の就労について」
講師:バーチャル工房山梨 副理事長 田崎輝美 様
支部だより
富士河口湖支部
先頭に戻る
目次へ
支部長 近藤とみ子
コロナウイルスの感染が増す中、先日の総会で管内に音声信号機の敷設の情報を得ましたので確認に行ってきました。1車線往来の車道の片側に小学校の入り口とコンビニ、反対側にもコンビニと交番があり駐車スペース出口付近に押しボタン式の信号機がありました。安全を確保するためにもこの信号機を使いたいと思います。
事務局よりお知らせ
甲府市から要望の回答がありました
先頭に戻る
目次へ
横沢通りの誘導ブロック及び交差点へのエスコートゾーンの設置について
- 『誘導ブロックについて』
- (1)共用開始された横沢通り東側歩道及び西側歩道への誘導ブロック設置につきましては、今年度、両側歩道に区画整理課が設置してまいります。
(2)朝日町ガード交差点から甲府駅までの南側歩道への誘導ブロック設置要望につきましては、甲府合同庁舎北交差点から甲府駅までの区間は、既に整備が完了しております。引き続き、まちづくり部まち整備室都市整備課が、歩道改良工事の進捗と併せて残りの個所を整備してまいります。 - 『横沢通りと飯田通りの交差点へのエスコートゾーンについて』
- (1) 今年度、区画整理課が設置してまいります。
中央4丁目交差点工事についてのお知らせ
道路の拡幅工事のため約1年間にわたり、工事が続きますので付近を歩行の際はご注意ください。詳細につきましては、連絡が入り次第お知らせします。
バリアフリー演劇 ヘレン・ケラー〜ひびき合うものたち
先頭に戻る
目次へ
令和3年度山梨県障害者文化芸術フェスティバル開催事業
- バリアフリー演劇 ヘレン・ケラー〜ひびき合うものたち
出演:東京演劇集団 風
日時:11月3日(祝・水)13時〜15時25分
会場:日野春學舎(旧日野春小学校)
音声ガイドをオープンで会場に流し、物語の進行を創造的に補う方法で情報保障を行います。
ご覧になりたい方は事務局小林まで希望の人数をご連絡下さい。
第2回視覚障害者リモート将棋大会のお知らせ
先頭に戻る
目次へ
- 日時 12月11日(土)・12日(日)
対局方法 ZOOMを使用してオンライン対局を行う
参加費 2,000円
申込は11月19日(金)までです。
開催要綱、申込書が必要な方は事務局までどうぞ。
マイナンバー制度の広報用資料について
先頭に戻る
目次へ
視覚障害者向けのマイナンバー制度の広報用資料を希望者に差し上げます。
10月から保険証としても使える予定の「マイナンバーカード」の広報資料がデジタル庁から届いています。点字版、音声版(音楽CD)、大活字版の媒体があります。希望者は、事務局までどうぞ。
編集後記
先頭に戻る
目次へ
編集後記 山梨県でも新型コロナの新規感染者が減少傾向を見せるなか、感染症の専門家らが懸念しているのが、冬にくるであろう“第6波”です。そんな中、興味深い記事を見つけたので紹介します。
以下、抜粋
この1年半を振り返ってみても、現在の感染対策(マスク、手指消毒、ソーシャルディスタンス)と人流抑制だけでは、十分に感染を抑えられていない。今の対策に限界があるのは、誰が見ても明らかだろう。そんな状況を見かねて、声を上げたのが東北大学大学院理学研究科の本堂毅さんほか、38人の科学者だ。
「これまで接触感染と飛沫感染が主なものとされていた感染ルートが、研究の進展によって接触感染はまれであることが判明する一方、これまでまれだと考えられていた空気感染が主な感染経路であることがわかってきました」
事実、今年5月には、CDC(アメリカ・疾病対策センター)も空気感染が新型コロナの重要な感染経路と言及した。「空気感染とは、“空中を浮遊するエアロゾルを通して染が広がる(airborne infection)”という意味であり、ウイルスの感染力の強さとはまた別の話です。大事なのは、空気と一緒に滞留するウイルスに対して、どう対策をとるべきかなのです」
昨年も話題になったエアロゾルとは、どんなものなのか。これについては、室内の空気清浄に詳しい工学院大学工学部建築学科教授の柳宇さんが説明する。
「エアロゾルとは、固体、あるいは液体の物質とまわりの空気が混ざった粒子のこと。大きさも定義されていて、0.001〜100ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリ)のものをいいます」
エアロゾルは重力によって落下していくが、その速さはかなりゆっくりだ。柳さんによると、5ミクロンのエアロゾルを、人が立っているときの口や鼻の高さである1.5メートルから落下させると、気流がまったくない状況でも35分間かかるという。
「エアロゾルの落下は温度や湿度、気流などにも大きく影響され、気流があればそれにのってどこまでも運ばれます。つまりエアロゾル感染=空気感染なのです」
では、どんな空気感染対策をとればいいのだろうか。本堂さんは言う。
「ポイントは、“空気の溜まり場を作らない”です。そのためには適切な換気が大事で、必要に応じて補助的に空気清浄機を活用します」
2つの「空気感染対策」が必要だ
- ① 適切な換気
- 厚生労働省も新型コロナ対策として、換気を呼びかけている。ただ、日ごとに気温が下がってくるこれからの季節、窓を全開にして換気するのは、現実的ではない。寒さを我慢して風邪を引いてしまうようでは、元も子もないだろう。
とはいえ、本堂さん、柳さんがすすめるのは、ずっと窓を開け続ける「常時換気」だ。30分に1回、窓を開けるなどのいわゆる「こまめな換気」は×。なぜなら、窓を閉めている間は気流が生まれず、空気のたまり場ができてしまうからだ。柳さんが言う。
「例えば、30分に1回、換気をしていたとしましょう。そこに感染者がいて、くしゃみをした場合、ウイルス入りのエアロゾルは30分以上、室内にとどまっていることになります。その空気を同じ部屋にいるほかの人が吸い込めば、当然ながら感染リスクは高まります」
寒い季節でも可能な常時換気のポイントとして、柳さんは「開けるのは必要な窓だけにとどめ、こぶし1つ分だけ開ける」ことをすすめる。
「このときに意識したいのは“空気の通り道”です。空気が部屋をくまなく流れるためには、対面の窓を1カ所ずつ開けるのが望ましい。開ける幅は5〜10センチで十分です」
なぜ1カ所の窓開けではダメかというと、それでは空気の出入り口ができないからだ。開けている窓の周辺は換気ができても、部屋の奥には新鮮な空気が届かず、空気のたまり場ができてしまう。よって、換気の意味をなさないというわけだ。
この常時換気をサポートするのが、マンションやアパートなどでは各部屋についている丸や四角の換気口(通気口)。ここはつねに開けておくことで、換気の効果が高まるという。
もう1つ、常時換気の強い味方がレンジフード(換気扇)だ。
「レンジフードは風量が大きいうえ、室内の空気を吸い込んで外に排出する機能を持ちます。室内が陰圧になるので開けた窓や換気口からは新鮮な空気が入り、空気の通り道を作ってくれるのです」(柳さん)
実際、柳さんらが行ったシミュレーションによると、換気を何もしていない場合は1分ぐらいで人の呼気から出たエアロゾルがリビングから部屋全体に広がるが、1カ所の窓を開けてレンジフードをオンにした場合、エアロゾルはレンジフードに吸い込まれていき、室内に広がることはなかった。
同じような意味で、トイレや風呂場の換気扇も常時、回しておいたほうがいいという。
換気中の暖房に関しては、ガスファンヒーターのように動かせるものであれば、できるだけ窓の近くに設置する。そうすると冷たい外気が暖房で暖まって部屋に入るので、室温を大きく下げることはないそうだ。
本堂さんは、今後、室内換気に重点を置きたいと考える人には、「熱交換器型換気機器(熱交換器)」の設置をすすめる。ビル換気でも使われている方法で、エアコンのようにあとからでも取り付けることができる。
「1時間に5回程度空気を入れ換えられるような、十分に換気量がある機種を選ぶことが大切です。本体だけでなく工賃もかかりますが、取り入れる外気を室温に近い温度にできるので省エネになります」(本堂さん)
なお、換気は“誰が感染しているかどうかわからない”といった状況で役立つ対策であり、感染者や濃厚接触者が判明しているときは、換気だけでは十分ではない。部屋を別にする、共有部分の消毒などの対策が別途必要になる。
(事務局長 小林誠)
山視協だより 令和3年10月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400−0005 山梨県甲府市北新1−2−12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 堀口 俊二
編集責任者 事務局長 小林 誠
電話 055−252−0100
FAX 055−251−3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
先頭に戻る
目次へ
過去の情報はこちらから