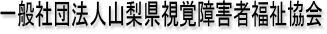山視協だより 令和7年11月号
第143号 令和7年11月15日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
| 巻頭言 | |
|---|---|
| 拡大読書器 給付基準額の全国調査の結果について | ・・・・・2 |
| 行事報告 | |
| 「寿の集い」に参加して | ・・・・・4 |
| 文化祭を終えて | ・・・・・4 |
| 今後の予定 | |
| 就労生活部講演会のお知らせ | ・・・・・6 |
| ビジョンサロン開催のお知らせ | ・・・・・7 |
| 第二回環境調査実施日のお知らせ | ・・・・・8 |
| 支部・クラブだより | |
| 甲州支部 | ・・・・・8 |
| 「寿の集い」に参加して | ・・・・・9 |
| 事務局より | |
| 募金の報告 | ・・・・・9 |
| 障害者の主張大会開催のお知らせ | ・・・・・9 |
| 日視連主催 第5回・6回視覚障害公務員交流会開催のご案内 | ・・・・・9 |
| お知らせ | ・・・・・11 |
| 編集後記 | ・・・・・11 |
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
巻頭言
拡大読書器 給付基準額の全国調査の結果について
先頭に戻る
目次へ
会長 小林誠
日視連では、今年8月に各団体の所管する地域において、令和7年7月末の時点で拡大読書器の給付基準額が198,000円を超えている自治体名とその基準額を全国調査し、その結果が公表されましたので、関東地区及び隣接する静岡県についてお伝えします。
- 1.調査概要
- 実施期間:令和7年8月7日(木)から9月30日(火)
対象:日視連加盟団体(60団体) 回答数38団体 - 2.給付基準額が198,000円を超えた自治体リスト(関東及び静岡県)
- ★印は今回の調査で給付基準額の変更が確認できた自治体
- 栃木県
- ・那須塩原市 226,000円
・大田原市 226,000円
・那須町 226,000円 - 群馬県
- ・★前橋市 204,000円
・★伊勢崎市 239,000円 - 埼玉県
- ・★さいたま市 239,800円
・★春日部市 248,000円 - 東京都
- ・★足立区 238,000円
・★千代田区 250,000円
・八王子市 400,000円
・東久留米市 268,000円 - 千葉県
- ・成田市 217,800円
・八街市 238,000円(据置型)、148,000円(携帯型) - 神奈川県
- ・★厚木市 250,000円
・★大和市 269,000円 - 山梨県
- ・甲府市 203,660円
・★早川町 217,800円(非課税世帯のみ) - 静岡県
- ・熱海市 250,000円
・裾野市 250,000円
・牧之原市 250,000円
・藤枝市 250,000円
・富士宮市 250,000円(次年度より改正予定)
・富士市 250,000円(次年度より改正予定)
・磐田市 250,000円(次年度より改正予定)
・掛川市 250,000円(次年度より改正予定)
・浜松市 250,000円(次年度より改正予定)
この資料を今後、拡大読書器の給付基準額の増額に向けた要望活動にお役立てください。
行事報告
「寿の集い」に参加して
先頭に戻る
目次へ
小林信一
9月28日(日)に行われた「寿の集い」に初めて参加させていただきました。会場の防災新館も初めてで、広く素晴らしい施設で感激しました。
長寿会員の方々も私のよく知っている人が多く、こんな先輩方々の御活躍があったからこそ、「現在の山視協」があるのだと、感謝一杯で込み上げて来るものがあり、ちょっとヤバかったです!
昼食の弁当も素晴らしく、あちこちで感激の声が聞こえて、美味しくいただきました。
午後の講談までの時間もたっぷりあって、心ゆくまで多くの先輩方々と対話することができました!
午後の「講談」も言葉さえ知らず、全国でも数少ない講談師「旭道南文字」先生と出会い、貴重な講談を聴くことができて感激し通しでした。
この「寿の集い」は、生涯の思い出になるでしょう。
最後に、今回の集いに携わった役員の皆さん、ヘルパーの方々、本当にありがとうございました!お疲れ様でした〜
文化祭を終えて
先頭に戻る
目次へ
埜村和美
第57回県下視覚障がい者文化祭は、10月19日(日)、会員とヘルパー49名の参加により、山梨県防災新館のオープンスクエアにおいて開催されました。
第1部の「点字の世界を広げよう」では、最初に点字の歴史や点字への思いについて、藤野ます子会員から提言がありました。フランスのシャルル・バルビエは11点の点字を12点点字に改良し、その後ルイ・ブライユが6点点字としてさらに改良を重ね、世界で使われるようになりました。日本ではブライユ式点字を基に、盲学校教諭だった石川倉次が五十音の方式に改め、その後点字新聞や点字投票、
点字受験など、視覚障がい者の生活と文化の扉が開かれていきました。
藤野さんは人生を広げてくれた点字を、大切にしていきたいと結びました。
会員からは簡易型の点字器の使用者やブレイルセンスの利用者もいて、日々の点字利用の体験が述べられました。40歳くらいになると点字の習得が困難になるといわれる中、そのころから点字習得に挑戦し、今では読書が日々の楽しみになったなどの意見もあり、努力が道を開くことを確信しました。点字研修会の持ち方についての意見もあり、点字考案200年を迎える今年、有意義な討論会になりました。
午後の文芸選評では、会員から投稿された俳句・川柳・短歌の作品が、青い鳥音訳者の穂坂由美子さんから朗読されました。日頃の生活や季節感あふれる様々な作品を味わいました。
文化講演会は、東京バラライカアンサンブルのメンバーをお招きし、第1部はこの日のためにユニットを組んだという、ショコラート(バラライカ山根綾香氏・ギター本田健二氏)による『カリンカ』に始まり『夢想』・『ロマンス』などが演奏されました。第2部は山梨で山根氏からバラライカを学んでいる、ララバラライカの皆さんがショコラートのお2人に加わり、『行商人』や『ララノテーマ』などがダイナミックに演奏されました。演奏会の進行役の広瀬信雄氏はララアンサンブルでコントラバスを担当していて、当日は数台のバラライカを持参してくださいました。そして会員はバラライカに触れたり、開放弦のラとミの音をはじきながら、演奏者との合奏を楽しみました。最後に会員が『100万本のバラ』をバラライカに合わせて合唱し、会場は大変盛り上がりました。
こうして会員同志の交流を深めながらの文化祭は、参加者の心にぬくもりを残しながら閉会しました。
今後の予定
就労生活部講演会のお知らせ
先頭に戻る
目次へ
就労生活部長 酒井 弘充
12月7日(日)、就労生活部主催による講演会を開催いたします。今年度は、日本視覚障がい情報普及支援協会(JAVIS)をお招きし、音声コード「Uni-Voice」の概要や、専用スマートフォンアプリ「Uni-Voice Blind」の紹介を行います。
みなさんは、山視協だよりやお知らせなどの右下に半円形の切り欠きがあることをご存知でしょうか。これがUni-Voiceが印刷されていることの目印です。日本年金機構からのお知らせ「ねんきん定期便」や、いくつかの保険会社からの「契約内容のお知らせ」にもUni-Voiceが採用されています。今回の研修会ではこのUni-Voiceを読み取る専用アプリのUni-Voice Blindについて実際に操作しながら研修していきたいと思います。現在、Uni-Voiceは市町村などの公的機関からのお知らせにも徐々に導入されつつありますが、今後は視覚障がい者を対象としたお知らせに限らず、様々なものにこのUni-Voiceが導入されてくれば、我々視覚障がい者の情報バリアフリー推進につながると思います。
さらにこのUni-Voice Blindというアプリには様々な便利な機能が搭載されています。特に注目すべきは、「耳で聴くWebポータルサイト」と「耳で聴くハザードマップ」です。「耳で聴くWebポータルサイト」は、生活圏の情報を直接耳で聴くことができます。情報の中にはWebサイト内のPDFデーターなどスクリーンリーダーで読み上げにくいものもありますが、これらのファイルはシームレスな音声情報の電子カタログとして提供されています。また、「耳で聴くハザードマップ」は、現在地や地点検索した場所のハザードマップの情報を音声で提供する機能です。浸水、土砂災害、火山災害などに対応しており、事前に居住地の災害リスクに関する情報を把握することができます。そして、万が一の避難の際には役に立つ、現在地から近距離の災害種別に対応した避難場所を表示、ルート表示、誘導する機能が装備されています。
しかしながら、現時点では、山梨県に対応したハザードマップは完成してはいるものの、アプリへ実装されていません。これは、県や市町村が、日本視覚障がい情報普及支援協会(JAVIS)と契約を結ぶ必要があるためです。すでに多くの都道府県が契約を締結しており、山梨県でも危機管理課や障害福祉課が強い関心を示しています。
今回の研修会を通して、我々視覚障がい当事者がこれらの情報を広く知り、山梨県における「耳で聴くハザードマップ」実装への機運を高めていきたいと考えています。
- 開催概要
- ・日時:12月7日(日)13時から(受付12時30分から)
・会場:やまなし地域づくり交流センター(エミフル)4階大会議室
・参加形態:ハイブリッド形式(会場またはZoomによるオンライン参加)
※オンライン参加をご希望の方は、12月5日(金)までにお名前と連絡先メールアドレスを事務局までご連絡ください。
ビジョンサロン開催のお知らせ
先頭に戻る
目次へ
山視協では、偶数月の第2土曜日にビジョンサロンを開催しています。ビジョンサロンは「見えない」「見えにくい」といった視力に支障があって、不自由さや困難さを感じている人を対象に情報交換や交流を目的としたサークルです。10月開催時は口コミや案内チラシを見て、初めての方を含め、20人前後の方が参加してくれました。次回は12月13日(土)です。ぜひお立ち寄りください。
- 参加無料、予約不要、出入り自由!
日時:12月13日(土)13時から16時
場所:山梨県立図書館交流ルーム102
第二回環境調査実施日のお知らせ
先頭に戻る
目次へ
福祉部部長 角田政樹
皆さん、こんにちは。来たる12月14日(日)に第2回環境調査を実施いたします。
今回は会員様より要望あった公共のトイレについて調査いたします。甲府駅並びにその周辺にあるトイレが対象です。私たちと一緒に調査に参加してみたいと思われる方は、事務局までご連絡ください。
日時:12月14日(日)9時30分から
集合場所:甲府駅南口階段下
締め切り:11月30日(日)
支部・クラブだより
甲州支部
先頭に戻る
目次へ
支部長 矢崎 繁
私たちの今年度の主な活動を紹介します。
定期総会を4月21日(月)に行い、総会終了後懇親会で親睦を深めました。
年間行事としては、定期総会、役員会2回、ブラインドウヲーク、体験教室、日帰り交流会が主な行事となります。内容は次の通りです。
6月2日(月) ブラインドウヲーク(韮崎大村美術館) 館内2グループに分かれ対面にて作品説明を受け、「蛍雪寮主屋」の見学し説明を受けました。懐かしかったのは庭先にあったポンプ式の井戸でした。帰りにはJA梨北農産物直売所にて買い物。小江戸甲府花小路にて散策と休憩で岐路につきました。
10月6日(月) 体験教室(吉田のうどん) 富士山北麓は冷涼な気候、そして火山灰や溶岩に由来し稲作に適さなかったので、麦作が行われ、伝統的に小麦を中心とした粉食料理が日常食とされていたそうです。また江戸末期から昭和にかけて、郡内地方における基幹産業は女性が携わる養蚕や機織だったため、男性たちは養蚕や機織で忙しい女性に代わって炊事を受け持ち、女性が機織りを止めずに食べられる昼食としてうどんを打ったとのこと。さらに男性の強い力で地粉をこねて、
コシ、硬さ、太さに特徴を持つ吉田のうどんが育まれたと言われています。
そんなうどんをこねて伸ばして切る料理を体験し、おいしく食べてきました。
11月7日(金) 日帰り交流会(静岡方面) 沼津御用邸記念公園見学と散策、伊豆フルーツパークにて昼食とみかん狩り、伊豆めんたいパーク、わさびミュージアムに行き、帰りに沼津港にて買い物の予定です。
「寿の集い」に参加して
先頭に戻る
目次へ
長寿会会長 藤野 ます子
9月28日(日)防災新館オープンスクエアにおいて寿の集いが行われました。最初に山視協会長挨拶があり、福祉部部長挨拶があり、続いて長寿会会員の
自己紹介、当日の参加者紹介がありました。その後食事になりました。
今年度からこの会の形式が変わり、お弁当を食べながら相互の交流を深めるということになりました。みんな久しぶりに友と会い、話が尽きないようでした。私も何年かぶりにお会いした方と話をすることができました。
寿の集いも長年行われていますが初期の頃は、長寿会の会員の人数も多くとても活気がありました。そしてマッサージコーナーがあり、女性部もお手伝いをさせていただきました。会員の皆様もとても喜んでくださいました。
この会を企画してくださった福祉部の皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。
事務局より
募金の報告
先頭に戻る
目次へ
去る10月19日(日)、文化祭の際に11,732円の募金が集まりました。多くの皆様からのご協力をいただき深く感謝しております。
大事に使わせていただきたいと思います。ありがとうございました。
障害者の主張大会開催のお知らせ
先頭に戻る
目次へ
- 開催日時:令和7年12月6日(土)13時30分から
場所:山梨県防災新館1階 オープンスクエア - 開催当日から令和8年3月31日(火)までYouTubeで配信します。(YouTubeで「バーチャル工房やまなし」と検索)
- プログラム
- 1 開会 主催者挨拶、審査員紹介
2 障害者の主張大会
3 講演 「法と社会−誰もが生きやすい社会を実現するために」
日本大学法科大学院客員教授・弁護士 須藤 典明氏
4 表彰式 主張大会表彰 主張大会講評
やまなし心のバリアフリー推進ポスター・標語表彰
5 閉会
聴講は事前申込となっております。(山障協 坂村さんまで)
日視連主催 第5回・6回視覚障害公務員交流会開催のご案内
先頭に戻る
目次へ
第5回視覚障害公務員交流会:2025年12月6日(土) 13時から16時30分
第6回視覚障害公務員交流会:2026年2月14日(土) 13時から16時30分
会場参加(日本視覚障害者センター)とオンライン(Zoom)を交えたハイブリッド方式で行われます。
これまでの4回の交流会の中で出された、困りごとや意見をもとにテーマごとに参加者の経験や意見を聞き、これからの公務部門で働く視覚障害者の職場環境の改善を目指します。
公務員として働いている方でご興味のある方はお申し込みください。
申し込み・お問い合わせ先:日視連総合相談室
電話 03-3200-6169(情報部)
メール soudan@jfb.jp
ホームページは次のリンク先からどうぞ。
日視連ホームページはこちらから
お知らせ
先頭に戻る
目次へ
国民生活センターから見守り新鮮情報が発行されました
見守り新鮮情報は、高齢者・障害者等に注意してほしい消費者トラブルや事故情報をわかりやすくお伝えするため、国民生活センターが発行しています。
国民生活センターの見守り情報は、以下のリンク先よりアクセスいただけます。
見守り情報
2026年りそなグループ点字カレンダー(20部)
日本盲導犬協会「盲導犬くらぶ」(墨字、点字、音声CDが1部ずつ)
ご希望の方は事務局までご連絡ください。
編集後記
先頭に戻る
目次へ
皆さん、この秋いかがお過ごしでしょうか?山視協では寿の集い、文化祭などイベントが目白押しでした。
この山視協だより143号がお手元に届くころには創立70周年記念大会も無事終わっていることと信じています。
この原稿を書いている今、私の耳にも11月の声が届いてはいますが、山視協のあれこれに没頭し、季節を見失ってしまいそうです。とはいえ、一つ一つのことは成し遂げ、そのために多くの方々のご協力をいただき、新たな出会いもあり感謝の気持でいっぱいです。
(事務局長 小笠原恭子)
山視協だより 令和7年11月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400−0005 山梨県甲府市北新1−2−12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 小林 誠
編集責任者 事務局長 小笠原恭子
電話 055−252−0100
FAX 055−251−3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
先頭に戻る
目次へ
過去の情報はこちらから