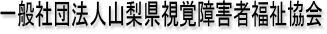山視協だより 令和6年1月号
第121号 令和6年1月16日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
| 新年のご挨拶 | |
|---|---|
| 会長・副会長 | ・・・・・2 |
| 行事報告 | |
| 第3回役員会報告 | ・・・・・5 |
| 就労生活部研修会の報告 | ・・・・・7 |
| 編集後記 | ・・・・・8 |
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
新年のご挨拶
会長・副会長
先頭に戻る
目次へ
新年のご挨拶
会長 埜村和美
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年4月の総会に於いて、会長の責を担うようになってからはや9か月が過ぎようとしています。コロナ禍に明け暮れたこの数年間でしたが、昨年5月より5類として認定されたことにより、注意を払いながらも当会の事業が少しずつ展開されるようになりました。この数年の間にはコロナ禍も影響してか、社会のデジタル化が急激に進んだように思います。当会の活動の重点課題として、移動・情報・就労の問題がありますが、年明け早々に発生した能登半島地震に鑑み、災害に弱い立場である私たち障がい者の災害時の対策も差し迫る問題として取り組まねばならないと思いました。
日本は人口の減少が異常な速さで進んでおり、駅や商業施設・飲食店などで人の手を借りることが非常に難しい状態になりつつあります。安全な移動やスムーズな社会参加のためにも、声を上げていかねばなりません。より良い生活の確保のためにはまだまだ問題が山積していますが、会員の皆様と共に手を携えながら運動して参る所存です。皆様のご協力を心からお願いいたします。会員の皆様のご健康とご多幸をお祈りして、挨拶に代えさせていただきます。
新年のご挨拶
副会長 小田切浩子
明けましておめでとうございます。
令和6年辰年が始まりました。辰年は陽の気が動いて万物が振動するので、活力旺盛になって大きく成長し、形がととのう年だといわれています。皆様にとって充実した一年になりますようお祈り申し上げます。
本会も昨年はやっと対面にて行事を行うことができました。やはり実際にお会いして皆様のお声を聞くことができたことは嬉しいことです。今年もみなさんに参加していただけるような行事を行ったり、ご意見を頂きながら会の活動に携わって参りますのでよろしくお願いします。
新年のご挨拶
副会長 小林誠
会員の皆様、また本誌をご購読の皆様、あけましておめでとうございます。
例年なら穏やかな新年をと申し上げるはずでしたが、今年の年明けは、二つの大きな事件からスタートとなってしまいました。
まさか元日から大地震が起こってしまうなんて思ってもいませんでした。確かに地震災害についてはいまだ予知することは不可能ですが、大自然の力の大きさを再確認した出来事でした。そして、平凡で穏やかな日々が送れることがどんなに幸せなことかと思い知らされました。
さて、今年4月1日から改正障害者差別解消法が施行されます。大きな変更点は、事業者に対し、合理的配慮がこれまでの努力義務から義務に変更になることです。この改正により、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる共生社会に一歩でも近づくことを期待したいと思います。
最後に昨年に引き続き、今年も当会に対し変わらぬご理解、ご協力よろしくお願い申し上げます。今年一年が皆様にとりまして健やかで安全な年でありますよう、心からお祈り申し上げます。
新年のご挨拶
副会長 名取利一
新年明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては穏やかな年明けをお迎えのこととお喜び申し上げます。
コロナウイルス感染症に関し、昨年6月に5類に格下げされたものの依然として不安な状況が続いています。私が現在一番気がかりなことは、感染者に対し外出の自粛要請はあるようですが、いつでもどこでも自由に出かけることが認められていることで、感染者にいつ・どこで遭遇するか判らないことです。
また、新年早々、羽田空港で発生した民間機と海上保安庁機の衝突事故もその一つになりますが、石川県を中心とした震度7を記録する大震災が起こったことです。津波の発生、ビルや木造建築物の倒壊、火災の発生、広範囲に渡る停電・断水など、逐次被災状況が報告されています。このような発言をすると被災地の方には叱られますが、1月3日時点での犠牲者が100人未満だと言うことです。これ以上の犠牲者が増えないことを祈る次第です。
念頭から触れたくないような挨拶となってしまいましたが、私が現時点で特に気になったことをスナオに書かせていただきました。どうかお許しください。
最後に、今年の干支は辰年、辰年というと「幸せを招く」年だそうです。会員の皆様のますますのご健康とご多幸をお祈りし、年頭のご挨拶とさせていただきます。
行事報告
第3回役員会報告
先頭に戻る
目次へ
事務局長 小林誠
第3回役員会を12月17日午前10時から地域づくり交流センターを会場にハイブリット形式で行いました。埜村会長のあいさつに続き、議事に入りました。
- 事務局から
- 前回の役員会以降の経過報告があり承認されました。続いて各部からの事業報告と今後の予定が報告されました。
- 就労生活部から
- 11月19日の県民の日のふれあいマーケットに「マッサージフェスタ」を出店し、施術者11名で116人を治療しました。その際、有資格者と無資格者の違いをアピールし、1万円余りの募金があったそうです。
- 次に体育文化部から
- 9月10日に研修旅行を行い、45名の参加がありましたが残暑が厳しく今後実施時期を検討する必要があるとの意見が出ました。11月11日に文化祭を行いました。午前中は、これまでの点字競技会に変えて「点字の世界を広げよう」という新しい企画を試みたが、おおむね好評だったようです。午後からの講演会も実際に土器に触れることができ貴重な体験でした。今回、開催が土曜日だったので曜日については今後検討してゆきたいとの報告でした。
- 福祉部から
- 8月20日の「あしらせ体験会」は、猛暑だったので、室内での体験会となってしまったが参加者全員が体験できてよかった。9月24日には、4年ぶりに寿の集いを行い、部員配置やタイムスケジュールなど細かい点に反省すべき点はあるが来年に向けてより良い内容にしてゆきたい。11月12日今年度2回目のバリアフリー調査を行った。1月下旬に部会を開いて今年度の活動を振り返り、次年度の活動に生かしてゆきたいとの報告でした。
- 次の議題では
- 来年度の定期総会に向けて年明けから定期総会までの日程について事務局から報告がありました。
- 4番目の議題は
- 3月3日・4日に千葉県で行われる第58回関東ブロック協議会の日程と参加者の募集に関する説明が事務局からあり、多くの参加をお願いしたいと要望がありました。
- 続いて次の議題では
- 前述の関東ブロック協議会に本会から提出する議題が各部から報告されました。
- 生活分科会担当の福祉部からは
- 昨年同様、重度心身障害者医療費の窓口払いの無料化制度の法制化、並びにこの要件に課されているペナルティーの撤回を要望する。
- バリアフリー分科会担当の体育文化部からは
- すべての駅のホームに内方線付き点状ブロックを敷設するとともに、弱視者にも見やすい案内表示をつけること。
- 職業分科会を担当する就労生活部からは
- 視覚障がい者の雇用拡大のために、国の機関や公的機関、民間企業にヘルスキーパーの雇用を促すよう、積極的な取り組みを要望する。
これらの議題を本会から提案することが承認されました。 - 6番目の議題
- 定款検討委員会・名簿作成委員会からそれぞれ報告がありました。
まず、定款検討委員会から、変更が必要と思われるのは2か所。一つは、議事録署名の部分を一部変更し、署名または記名、押印にする。二つ目は、役員会通知は、現在の郵便事情を考慮して7日前を変更し5日前までとするに変更し、これまでの書面に加え、電磁的通知方法も加える。そして、これらの定款変更は、会員の3分の2の賛成を必要とするため、役員一丸となって対応することが確認されました。
続いて名簿作成委員会からは、名簿を再作成する目的を会員に説明し、協力を求めなければならない、次回以降、調査項目を必須項目と任意項目とに分類し、理解しやすい内容にしたいと報告がありました。また、参考意見として、新会員と退会した会員を役員会にて報告したらどうかとの意見がありました。 - 7番目の議題は
- 本会創立70周年記念について話し合いました。実施時期について令和7年6月もしくは、11月頃が他の事業への影響が少ないのではないかということで会場など情報を収集して次回の役員会で報告することになりました。
- その他では
- 令和7年度に関東ブロック担当の全国福祉大会が千葉県・千葉市合同で開催されることが関ブロ委員会で決定したことが報告されました。
- 情報交換として
- タクシー利用時にタクシーを呼ぶ際、迎車料金が加算され、利用者にかなりの負担になっていることが報告されました。
以上、第3回役員会報告です。
就労生活部研修会の報告
先頭に戻る
目次へ
就労生活部長 酒井弘充
就労生活部では12月17日(日)13時〜15時に地域づくり交流センター「エミフル」4階大会議室において「電子決済あれこれ」というテーマで研修会を行いました。
当日は就労生活部員が講師を務めるという手作り感満載の研修会で、会場に25名オンラインで若干名参加いただきました。まずはじめに酒井より電子決済の概要や種類、メリットやデメリットなどについて説明を行いました。その後、井口部員、小笠原部員、堀口部員と酒井がパネラーとなり、各自が使っている電子決済の種類やどのような場面で利用しているのか。また、実際に使用してみての使い心地や課題などについて情報を出し合いながら会場参加者も含めて意見交換を行いました。最後にスマートフォンを使ったQRコード決済である「PayPay]を操作し、支払いの画面まで表示させたり、実際にQRコードをスキャンしてみたりといった体験会を行いました。
本年度はじめて生活の分野で研修会を行ってみました。とはいっても実現可能な内容がなかなか見つかりませんでした。会員各位におかれましてはこんな生活に関連した内容の研修会などできないかといったアイデアをお知らせいただければ幸いです。
編集後記
先頭に戻る
目次へ
新年が明けて既に半月を過ぎ、皆様も通常の生活に戻られているころだと思います。昨年の5月以降は、外出の機会も増えコロナ以前の生活を取り戻しつつあります。今回取り上げる話題は、私が言うのも変かもしれませんが女性のメイクの話題です。
以下、マイナビニュースから
「ブラインドメイク ユーディー パレット」視覚障害者の発案で誕生
「ブラインドメイク」とは、元来「メイクに夢中」という意味の俗語ですが、視覚障害者が鏡やブラシを使わずに指を用いて自分自身でフルメイクができる化粧技法を示す意味で使われているのだとか。
今回紹介する商品は、視覚障害のある石垣愛華さんの試作品から生まれたという化粧パレット。
石垣さんは、以前は晴眼者と同じメイク道具を使用していましたが、定期的なフォルム変更や季節ごとに容器の形状、色彩、配置が変わるため、その都度色の配置や使用する量を覚え直す必要があったそうです。また円柱状のものは紛失のリスクがあるほか、容器の形状が似ているものは間違えることもあったといいます。
そこで同商品では、主要な9アイテムを1つのパレットにまとめることで、アイテム数を減らすとともに、アイテムを「クロックポジション」と呼ばれる時計の短針の位置に配置できるような仕様を採用。
また、左右が分かるよう3時と9時の位置の側面に小さな突起を付けたほか、各アイテムの間に線状の凸起を付けることで隣のアイテムに指が触れ、アイテムが混ざらないような工夫をしたそうです。
開閉口はパチンと音が鳴る形状を採用し、音で閉じたことが確認できます。パレットは1つ1つ取り外しができるほか、レフィルには品名とカラー名を点字で入れているとのこと。
SNSでは「素敵なアイディアだと思います」「すごーい ナイスアイデアだと思います」「『〇時の方向』で表しやすい配置なの良いねー」「工夫がすごい」「おジャ魔女の変身道具みたいで素敵」との声があがっています。
ユニバーサルデザインにこだわり開発されたこのパレット、視覚障害者に限らず、どんな人にも使いやすくなっているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。
視覚障害者の生活の工夫から生まれたまさにユニバーサル製品といえますね。
(事務局長 小林誠)
山視協だより 令和6年1月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400−0005 山梨県甲府市北新1−2−12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 埜村 和美
編集責任者 事務局長 小林 誠
電話 055−252−0100
FAX 055−251−3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
先頭に戻る
目次へ
過去の情報はこちらから