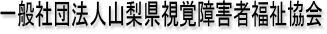山視協だより 令和7年1月号
第133号 令和7年1月15日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
| 新年のご挨拶 | |
|---|---|
| 正副会長の新年のご挨拶 | ・・・・・2 |
| 行事報告 | |
| パネルディスカッションに参加して | ・・・・・4 |
| 「見えない壁だって乗り越えられる」を聴いて | ・・・・・5 |
| 第3回役員会報告 | ・・・・・7 |
| 就労生活部講演会報告 | ・・・・・10 |
| 支部だより | |
| 峡南支部 | ・・・・・11 |
| 事務局からのお知らせ | |
| 甲府市内(城東病院南側)の道路工事について | ・・・・・12 |
| 障害者の主張大会報告 | ・・・・・13 |
| 山梨県障害者文化展(総合展)開催のご案内 | ・・・・・13 |
| 日視連主催第50回記念全国視覚障害者文芸大会入選作品「ささやかな語りを夢みて」 | ・・・・・13 |
| 編集後記 | ・・・・・17 |
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
新年のご挨拶
正副会長の新年のご挨拶
先頭に戻る
目次へ
新年のご挨拶
会長 埜村和美
謹んで新春のご挨拶を申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。昨年1月1日に発生した能登半島地震から1年が経た今、大水害を含めていつ災害に見舞われるかと、我が防災対策を振り返る日々です。災害時の一刻も早い救助活動の観点からも、当会では昨年秋から名簿の再構築をしています。皆様のご協力を得て、全体の3分の2以上の会員の再登録が終了しました。引き続きのご協力をお願いいたします。
視覚障がいに高齢化の進む会員の多い中、災害時に取り残されないためにも、合理的配慮の生き届いた避難所が確保されるよう、会として真剣に取り組んでいきたいと思います。また益々進むデジタル化の中、スーパーや飲食店などでの利用がスムーズにできなくなってきました。障害者差別解消法の観点からも、障がい者に対する企業側からの人的配慮が容易に受けられるよう、声を上げて参ります。
その他、当会の課題として、移動や情報のバリアフリー化など、引き続き進めていかねばならない問題があります。点字ブロックや音響信号機の敷設がまだまだな地域や、同行援護事業所のない市町村など、山積する問題の一つ一つの解決のためにも、地道に努力していきたいと思います。
会員皆様方のご協力を心からお願い申し上げます。本年が皆様にとりまして健康で穏やかな日々でありますよう心よりお祈りして、新年のご挨拶とさせていただきます。
新年のご挨拶
副会長 小田切浩子
新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。
巳年は脱皮をする蛇のイメージから「復活と再生」を意味します。植物に種子ができはじめる時期、次の生命が誕生する時期など、新しいことが始まる年になると言われています。また、「巳」を「実」にかけて「実を結ぶ」年とも言われるようです。本会も今年は70周年の記念行事を予定しています。皆様に参加していただけるよう準備を進めています。
これまでの歩みを大切にしつつ、更なる発展のために変革の年になればと願っておりますので皆様のご協力をお願い致します。
新年を迎えて
副会長 小林誠
あけましておめでとうございます。皆様方に置かれましては、おだやかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
昨年は、能登半島の大地震に始まり、豪雨被害が各地で発生し、記録的な被害を与えました。幸いこの山梨には大きな被害こそありませんでしたが、温暖化の影響でこれまでには起こりえなかった災害が発生していることも事実として受け止め、災害に対する認識を改めなければと感じました。
世界に目を向けると、ロシア・ウクライナ情勢、イスラエル・パレスチナ問題など世界的に不安定な情勢が私たちを物価上昇という形で生活を脅かしています。今年こそ、平和で穏やかな一年でありますことを皆さんと願いたいと思います。
さて、本会においては、今年11月に「創立70周年記念事業」が予定されています。この10年の歩みを振り返りつつ、現在の取り巻く課題を皆さんと語る機会となればと思います。どうぞ、ご協力をよろしくお願いいたします。最後に皆様に取って幸多き年となりますよう、お祈り申し上げます。
年頭のごあいさつ
副会長 名取利一
あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、つつがなく新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年の干支は巳年です。巳年と言えば新しいことが始まる年だと言われ、また、金運を招く年だとも言われています。昨年は自然災害が国内全体でみられましたが、今年こそ穏やかで過ごしやすい年になるよう、願ってやみません。
さて、今年は山視福協にとって70周年と言う記念すべき節目の年に当たります。先人の方々の努力の成果により現在に至っていますが、生活環境などについては、いまだ充分だといえる状況には至っていません。この大会を機にさらなる視覚障がい者の自立と社会参加促進に向けた新たな一歩となるよう、皆様方と共に歩んでいきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
結びに、皆様方にとって、最良の年になるよう祈願し、新年のご挨拶とさせていただきます。
行事報告
パネルディスカッションに参加して
先頭に戻る
目次へ
梶原剛
文化祭の午前の部は、「点字の世界を広げよう」という企画で、パネルディスカッションが開催されました。参加者は35名でした。パネリストの方は、小さいときから点字とかかわった方が2名、大人になってから点字を習い始めた方が2名でした。
4名のパネリストの方のお話を中心に、ディスカッションは進められました。電車での移動や買い物など、生活のいろいろな場面で点字を利用しているということが特に印象に残りました。また、トイレの点字表示を読むことができたときは、うれしかったというお話などは、中途視覚障がい者が点字を学習するときの目標になるように思いました。IT機器の実演やフロアからの意見や質問などもあり、和やかなパネルディスカッションとなりました。企画や当日の運営に携わっていただいたスタッフの皆さん、ありがとうございました。
なお、中途視覚障がいの方でこれから点字を学びたいと思われた方は、山梨ライトハウスの金山さんまで、お気軽にお問合せください。
電話番号は、055-224-5060(青い鳥成人寮)です。
「見えない壁だって乗り越えられる」を聴いて
先頭に戻る
目次へ
角田政樹
12月1日に体育文化部の講演会が開催されてより2・3日後の朝。洗面所で整髪をしている私の背中から声が。弟であり、体育文化部部長のたかちゃんより「おぅ、体育文化部の講演会の感想文を書いてくれ」と。「えー」と返す私。聖徳太子も2度聞きするほどの衝撃。春から福祉部関係で、告知文も含め、結構な頻度で投稿して参りました。まぁ、執行部や他部長、支部長や他様々な役についている方々に比べれば全然大した事は無いのですが、私にとって、スマホに文章を打ち込み、それを送信する事はなかなか骨の折れる作業です。11月の環境調査の報告文は次長が書いてくれることになったので、ここ2ヶ月位は文章を書かなくて済むと高をくくっていたところ、たかちゃんからのまさかの依頼。準備も何もしていなかったので、講師である小林さんの輝かしい戦歴も、講演の詳しい内容も書けません。ですが、報告文ではなく感想文と言われたので私がどのように感じたかのみを書かせて頂きます。
まず、この方、スケールがデカい。そして、行動力がハンパない。小林さんは「世界一になることが最終的な目標ではなく、世界を広げていくことが大事なんだ」と。地理的な意味での世界の大会で何度も優勝している小林さんが、最も目指しているものは、概念的な意味合いでの世界でした。すなわち、視覚障がい者と健常者が共に楽しめる世界(もちろん、クライミングを通して)の構築です。
このロマンあふれる夢の実現のため、日々のプチチャレンジ(一歩踏み出す勇気)を積み上げてゆく。小林さんはプチチャレンジと言っていました。確かに、雑誌の掲載先に電話をかける事はプチです。が、見えない身体で、どうしても直接話をしたい人に会うために、アメリカに行ってしまうなんて(これのどこがプチなんや)行動力凄すぎです。この方は心がとても強い方です。人を突き動かすのはその人の心です。もともと強い心をお持ちだったんでしょうが、見えなくなってから、そして自分の障がいを受け入れてから、より強くなったのではないでしょうか。
そう、小林さんは中途です。普通に健常者として大学まで進み、普通に健常者として企業に就職しました。普通に車も運転していました。そして社会人をやっている時、普段見えていたものがだんだんと見えなくなり、手帳を取れるまでに至りました。自分の病気が受け入れられず、何件かの医療機関を受診したそうです。抗いたかったんですね。多分。小林さんは「抗う」という言葉は使ってなかったと思いますが、私にはそう感じました。なぜなら、あの時の私はそうだったからです。私も中途です。社会人の時に手帳を取得しました。手帳を取得するに至るまでの経緯も、病院を何件も受診したところも同じです。あの時に感じた焦燥感、不安感、絶望感を思い出し、少し胸が痛みました。
ですが、そんな感情もつかの間。その後の話で「勇気」をたくさんいただくことができました。小林さんは、高校の時より続けていたクライミング、視覚障がい者を支援する機関の方々との出会い、そして何より、視覚障がい者でありながら、エベレストをはじめ世界の名だたる山を登った方に会うためアメリカまで行き、自分の思いを聞いてもらうことにより、見えない壁を乗り越えたのではないでしょうか。そして、なりたい、自分に続く道が見えたのではないでしょうか。それからは、持ち前のワールドワイドな視野と抜群の行動力で破竹の勢いです。
でも、壁は1つでは無いはずです。乗り越えた先にはまた分厚く、大きな壁があるのだと思います。この繰り返しですよね。この壁を超え続けていくことが、まさに人生そのものであり、より強く「こうなりたい」「これがしたい」と思う心を持ち、日々のプチチャレンジを積み上げることで、それはとても充実したものになるのだろう。と。
以上が私の感想文です。感じたこと、思ったことしか書いてませんので、講演会を聞いていない方にはわかりづらいかもしれません。独りよがりの文章ではありますが、私的には「勇気」を持って書かせていただきました(これってスケールちっちゃいな)。講演会の詳しい内容が知りたい方は、事務局にお問い合わせいただければ幸いです。
第3回役員会報告
先頭に戻る
目次へ
事務局長 小林誠
昨年12月15日(日)に地域づくり交流センターにおいて、今年度3回目の役員会が開催されました。
埜村会長のあいさつに続き、早速議事に入りました。
始めに、事務局関連の経過報告がなされ、承認されました。この報告の中には、関ブロ茨城大会に提出された本会からの各提案議題も含まれておりますので報告いたします。
【生活分科会】地域で同行援護を活発にするため、同行援護事業所を増やし、従業員数を確保すること
【バリアフリー分科会】テレビ放送において、緊急放送の字幕の音声化、並びに表示の拡大化を早期実現すること
【職業分科会】視覚障がい者の雇用拡大のために、国の機関や公的機関、民間企業にヘルスキーパーの雇用を促すよう積極的な取り組みを要望すること
追加報告として、堀口理事より、障害者差別解消ネットワーク会議において、「買い物の際のセルフレジの際、視覚障がい者にも使える機器の開発と導入もしくは、店員の配置をお願いした」と報告がありました。
次に各専門部から報告がありました。
就労生活部から、ふれあいマーケットのマッサージフェスタに100人の来場があり、2万2千円の募金があったそうです。
続いて、体育文化部から、10月20日の研修旅行について久しぶりの県外で良かったが反省すべき点もあり、今後に生かしてゆきたいとの報告でした。12月の文化祭では、点字の世界の第1部では、4名のパネラーによるディスカッションは、好評でした。2部の講演会は、外部からの聴取者もあり、44名もの参加者があり、予想を上回る反響との報告でした
福祉部からは、8月18日の講演会は「フレイル予防について」でしたが、今後の参考になる内容で良かったと思う。9月22日の「寿のつどい」は、和気あいあいとした雰囲気で楽しめたのではないかと思う。11月10日のバリアフリー調査は、春日居駅と東山梨駅のバリアフリー面で調査したとの報告でした。
3つ目の議題は、定期総会までの流れが事務局から告げられました。各部、各クラブ、事務局の総会原稿が1月末まで、2月16日事務局会議、3月23日役員会、4月20日定期総会となっています。
4番目の議題、「令和7年度の予算計画について」ですが、会計担当の吉村理事と小笠原理事から説明がありました。要約すると、本会の大半の収入である「書き損じはがき」の収入が、担当者の体調不良により、十分な陳情活動ができず、収入が未定であること、会員の減少により、会費収入が減少していること、行政の補助金が著しく減少したこと、などから、これまでと同じ事業を継続するには、年間100万円不足することが説明されました。
とりあえず次年度は、基本金から100万円を引き出し、その後については、何らかの事業をして収入を増やして行かないと本会の存続が不可能であるとの厳しい内容でした。支出面では、会計内規の内容をこれまでより切り詰めた内容にすることが検討され、承認されました。いずれにしても本会の財政が厳しい状況にあることを会員の皆様にもご理解しておいていただきたいと思います。今度の総会では、このことが重大な議題になることは間違いありません。
5つ目の議題は、定期総会終了後、どのような催しが良いか事務局から提案がありました。出席者からは、ミニサイトワールドのようなものができないかとの要望がありました。会場の広さなどの問題があるので、事務局の今後の検討課題となりました。
6番目の議題、創立70周年記念事業の準備状況の報告が、各担当の名取副会長と小田切副会長からありました。式典担当から、講師の都合上、講演会、式典、祝賀会の順番になる見込みであることが報告されました。記念誌担当からは、前回よりコンパクトなものにして、配布媒体も本人の希望する形で配布したいとのことでした。二人の報告に続き、事務局から、大まかな見積もりが公表され、今後の準備を進めることとなります。
7つ目の議題は、盲学校運営協議会メンバーに山視協から代表者を1名選出してほしいと盲学校教員の酒井理事から要請がありました。(その後、元盲学校の教師の堀口理事に決まりました。)
その他の議題として、これまで第2回の役員会を8月に対面で開催してきたが、気候の温暖化による影響を考慮し、今後は、オンラインによる会議に変更することになりました。
最後に会員名簿の更新がまだの会員に協力を促すことを確認して、役員会を終了しました。
就労生活部講演会報告
先頭に戻る
目次へ
就労生活部長 酒井弘充
就労生活部では12月15日(日)14時~16時に県立地域づくり交流センター「エミフル」4階大会議室において「成年後見制度の概要」というテーマで研修会を行いました。
講師は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター山梨支部の渡邊淳様をお招きして実施しました。渡邊様は行政書士会の中にある成年後見の責任者をされておられる方です。
まず、はじめに成年後見人制度を取り巻く状況についてお話しいただきました。この制度は2000年にスタートしたそうですが、高齢化社会が進行する一方で後見制度の利用がなかなか進まなかったそうです。そこで、第一期利用促進計画で、利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善がなされたそうです。さらに現在進行中の第二期利用促進では権利擁護支援と地域ネットワークの構築を進めているそうです。
また、後見制度の種類についてもご説明いただきました。後見制度には利用する本人の状況やニーズに合わせて大きく2種類あるそうです。ひとつめは法定後見制度です。これはすでに判断能力が低下している本人に対し、親族等の申し立てにより、裁判所が成年後見人を選任する制度だそうです。ふたつめは任意後見制度です。これは判断能力がある本人が公正証書により契約し、裁判所が監督人を選任後に発効し、代理権により財産管理、身上保護を行う制度だそうです。それぞれに特性があり、利用するための手続きも異なるそうです。そのほかにも後見制度の職務内容や利用するにあたりその手続きの流れなどをご説明いただきました。また、後見制度の費用については、後見制度を受けようとする本人の財産状況をかんがみ、裁判所が決定するとのことでした。
当日は会場から多くの質問が寄せられ、時間の関係で質問数を制限しなければならないほど、会員みなさまの関心が深かったと感じました。就労生活部では、今後も職業や生活に関係した講演会を計画していきます。会員皆様からのご要望もお聞きしたいと考えています。
支部だより
峡南支部
先頭に戻る
目次へ
支部長 大窪誠
明けましておめでとうございます。令和6年現在の峡南支部在籍会員数は4名となっています。
今年度はコロナの終息状況を見守りつつ、活動を休止しておりましたが、来年度には何かしらの活動を行いたいとの旨の会員様からご賛同を頂いております。しかし、直近においても全国的なインフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、そしてコロナの流行が報道されているのが気がかりです。
最後になりますが他支部会員様におかれましても2025年が良い年でありますように。
事務局からのお知らせ
甲府市内の道路工事に関するお知らせ
先頭に戻る
目次へ
副会長 名取利一
県の道路管理課より連絡があり、現在、甲府市内の朝気1丁目北交差点の西側(城東病院の南側の道路)から中央4丁目南交差点にかけ、道路拡幅工事が行われており、大型車両の出入りや、大型重機等の騒音により、この周辺を通行する際には、充分注意してくださいとのことです。
特に注意を要する箇所は、朝気1丁目北交差点から西進する道路と、甲府市立図書館の西側の道路を南進する交差点で、横断歩道は設置されていますが、信号機が設置されておらず、変則的な4つ角となっています。
また、東側の横断歩道の手前には、南北ともに車両侵入のガードが変則的に設置されており、注意しながら歩かないと衝突する危険性が極めて高い状態です。さらに、この交差点から南進する道路には東西ともに、それほど広くない歩道がありますが、この西側の歩道をそのまま北進していき、東に横断するための警告ブロックを過ぎ、2・3歩進むと少し高めの段差があり、やはり転倒する危険性が高いため、東側に横断するようにしてくださいとのことです。なお、現在、横断歩道の手前の警告ブロック、 及びエスコートゾーンは敷設されていませんでしたが、12月中には敷設していただけるようになっています。
以上のようにこの交差点は、危険性が高く、工事期間もまだ5年ぐらいかかるということで、通行する際は特に注意してください。また、この周囲の道路環境を解っている方は、迂回とはなりますが、1個南に下った信号機をさらに進み、善誘館小学校南の道路を利用することをお勧めします。
障害者の主張大会報告
先頭に戻る
目次へ
12月7日(土)、第35回山梨県障害者の主張大会が山梨県防災新館で開催され、本会から三尾麻美さんが出場し、努力賞を受賞されました。主張作文「クライミングに出会ってから」は山梨県障害者福祉協会のホームページに掲載されています。
山梨県障害者文化展(総合展)開催のご案内
先頭に戻る
目次へ
- 期日 1月24日(金)~29日(水)27日は図書館休館日のため閉館
会場 県立図書館イベントスペース
時間 午前10時~18時 但し最終日の29日は、14時終了
皆様お誘いあわせのご来場をお待ちしています。
日視連主催第50回記念全国視覚障害者文芸大会入選作品
先頭に戻る
目次へ
【随想・随筆の部】第2位
「ささやかな語りを夢みて」 山梨県 榊原佳美子
昨年の4月10日の夜、私は、自宅の2階の最上階から転落した。私は網膜色素変性症という難病で、24歳頃全盲となり40年以上見えない生活を続けてきた。その階段も日常的に使っていたにもかかわらず、右足を一歩前に踏み出したら、そこには何もなかったのだ。かけつけてくれた救急隊員に私は「頸髄損傷だと思います」と伝えた。救急車の中でも意識があり、病院に到着して指輪をはずされたのも覚えている。術後、意識が戻った時には、気管切開が施され声を失っていた。目が見えない上に声も出せず、周囲の方と意思の疎通ができない。それは、私にとって青天の霹靂に思えた。それから、過酷な入院生活が始まった。「生きていてくれてよかったと家族皆が思っている」という妹からの手紙を、若い看護師さんが涙ながらに読んでくれたことを覚えている。その手紙を支えに入院生活に耐えてきた。とにかく水が飲みたいのだが、誤嚥の心配があるため、口の中を潤すことしかできない。その水をもらうことすら、病棟の忙しさの中で「待って」と言われ、耐えなければならないのが苦痛だった。大木に身体を縛り付けられているような感覚に襲われ息もできないくらいになると、死にたいと思う程だった。一般病棟に移ってからさらに過酷になった。看護師さんの人数が足りず、待たされることが多くなったのだ。それでも、せん妄状態に陥った私に対処してくれる看護師の方々のご苦労を思うと、感謝の気持ちで一杯になる。
5月19日にリハビリテーション病院に移ってからは、声で呼ぶことができず、手も動かせないのでナースコールを押すこともできない私に、舌で上顎を鳴らす方法を考えて下さってずいぶん楽になった。それでも、自分の声が元通り出るようになるかとても不安で恐怖を感じていた。7月3日に、カニューレが入り、声が出るようになった時の喜びはどれ程だったか。周りの方々も大変喜んでくれた。今でもスタッフの方々のその声が甦る。
経管栄養の期間も大変苦しかった。3食とも口から食べられるようにしてほしいと涙ながらに訴えたのは8月20日だったと記憶している。
自宅介護になってからも気管切開部からの痰の吸引は必要になるとのことで家族が指導を受けていた。が、救急搬送され気管切開の手術をしてくれた医師への再度の受診を勧められ、気管切開が閉じられることとなった。病院を退院するまでに気管切開が閉じられたのは、最高の喜びだった。
9月28日に退院した。家に帰りケアマネージャーをはじめとして訪問看護師、ヘルパー、リハビリの方々、家族の支援で順調に介護生活が滑り出した。夫も全盲なのだが、毎日マッサージをしてくれた。秋には、息子の車に車椅子を乗せ、山里に行き鳥の声を聞いたり、もみじの絨毯の上を車椅子で押してもらいカサコソという音を聞いた。雪が降った時には、庭の小枝に積もった雪を頬に触れさせてもらった。庭に咲いた鮮やかな黄色い牡丹やピンクのバラやスイートピーの香りを嗅がせてもらったりもした。このまま順調な日々が続くと信じていた。
ところが、4ヶ月後の2月の下旬頃から寒暖差の影響からか、体調を崩すことが多くなった。頚髄損傷から起こる体温調節障害が顕著になったのだ。
自宅介護者のメインは長男であるが、私の多くの要求に答えきれず「自分にはもう無理」と匙を投げるような言葉を言われた時「それなら出ていってくれ」と言ってしまったこともある。それでも息子は、しばらくすると何事もなかったかのように接してくれた。また、ある時、妹に対する私の言葉から妹と激しく言い合ったことがある。後悔している私に息子は「自分がもし母さんの状態になったら、理性を失ってもっと騒ぎ暴れると思う。」また「ケアマネさんは、本人がこの状態を受け入れるのに2年や3年かかると言っていた。」と私を庇ってくれた。こんなにも私を想ってくれる息子がいる。
私は「ききみみずきんおはなしの会」に属し、35年以上もの間ボランティア活動を続けてきた。この会は、日本や世界の昔話、創作のお話を暗記し、子どもたちの前で聞いてもらうというものだ。「目が見えなくても覚えて語るのだからできるんじゃない。」と長男の同級生の母親から誘われたのだ。この会に入ったことで、私の世界はどんなに広がったか計り知れない。全国の語り手たちとの出会い、たくさんの数えきれないお話との出会いによって、私自身がどんなに心豊かな生活ができただろう。今回の事故でそれを続けていくことは不可能になったのだが、その仲間たちが今も自宅を訪ねてくれる。新しく覚えたお話を語ってくれたり、児童文学はもちろんのこと、こどもたちに実際に関わっている方々が書かれた本などを読んでくれたりする。昔からの視覚障がい者の仲間や私の二人の息子の同級生のお母さんたちも時々お喋りに来てくれる。
こんなにも私を想ってくれる息子や多くの仲間たちに恵まれている私は何と幸せ者だろう。なのに、体調を崩すと冷静さを失い、自制心を失くすことがたびたびあった。その度に自分の発した言葉を反省し後悔するが、同じことを繰り返してしまう。
私は3月からこの7月の退院までに3回の入院をした。この間、多くの看護師や介護士の方々にお世話になる中で、いろいろな思いをし、自分を見つめる機会になったと感じている。今、自宅での介護生活に戻り、残された命をどう全うできるか考えている。家族や助けてくれる妹との関係をどう作っていくか、自分自身の目標をどこにおくか。いつの日か、私の孫や甥や姪の子どもたちに私がこれまで語ってきた〝おはなし〟を聞いてもらえる機会が作れたらどんなにうれしいだろう。宿命は定められていると聞く。それは受け入れるしかないが、どう生きるかは私自身が決めていくことなのだと思う。これからも思いもよらない出来事が降りかかって来るにちがいない。私を想ってくれる多くの方々と共に乗り越えていきたいと思う。
編集後記
先頭に戻る
目次へ
読者の皆さんは、すこやかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。今年一年も「山視協だより」をよろしくお願いいたします。
さて、今回のニュースは、山梨交通バスで、この1月10日より、「ミライロID」が利用できるようになりましたので、このアプリについてお伝えします。
ミライロIDとは、障害者手帳を所有している方を対象としたスマートフォン向けアプリです。 ユーザーは、障害者手帳の情報、福祉機器の仕様、求めるサポートの内容などを「ミライロID」に登録します。そして公共機関や商業施設において、ユーザーが「ミライロID」を提示することで、障害者割引や必要なサポートをスムーズに受けられます。
では、ミライロIDが使えるようになるまでの手順を説明します。
- 1. ミライロIDのアプリをダウンロードする
- iPhoneの方は、AppStoreから、アンドロイドの方は、GooglePlayからミライロIDのアプリをダウンロードします。
- 2. アカウント登録する
- 最初にガイドが出るので「次へ」をタップしていきます。ログイン画面になったら、「アカウント登録はこちら」をタップ。アカウント登録画面が出るので、電話番号(SMS認証)、パスワード、障害特性の選択、使用している機器を登録します。障害特性と使用している機器に関しては、入力をスキップする事もできます。アカウント登録完了の画面が出たら登録が完了です。
- 3. アプリに手帳を登録する
- ホーム画面から「手帳を登録する」を選択します。
確認事項を読んだ後、登録する手帳の種類、名前、生年月日の情報を入力します。次に、障害者手帳の撮影をします。折り目ごとにそれぞれのページを撮影する必要があります。カバーがついたままの写真はNGになっているので、カバーから出すのを忘れないように撮影しましょう。撮影した画像を送信すると完了です。 - 4. 審査が完了すると画面表示が変更される
- 審査が完了すると審査中だった画面が切り替わります。私の場合は3営業日で申請が完了しました。画面が切り替わっていれば、実際のお店や施設で利用する事ができます。
- 次に、ミライロIDとマイナポータルを連携する方法です。
- ①ミライロIDアプリをアプリのホーム画面かマイナポータルのアイコンをタップ
②連携しても良いか確認する画面が表示されるので「連携する」を選ぶ
③自動でマイナポータルが立ち上がるので、マイナポータルで本人確認をした後、最後まで手続きを完了する
手順を最後まで進めるとミライロIDアプリのホーム画面の「マイナポータル」の部分に「申請中」と表示されます。申請中に、申請を取り下げる事はできません。 - 次は、ミライロIDの使い方・できる事について説明します。
- ミライロIDは、基本的には窓口や対面での支払い時にアプリを見せて利用します。
- ミライロIDの使い方一例
- ① 公共交通機関の利用の割引の際に証明書として使える
② アミューズメント施設を利用する際に割引でチケットが購入できる
③ 駐車場を利用する際に割引が使える
④ 近くのコンビニで割引クーポンがつかえる - まとめ ミライロIDのメリット・デメリット
- ミライロIDを利用するメリット 障害者手帳を取り出さなくて良い、割引やサポートが使える、公共交通機関や施設の障害者割引はさまざまな場所で利用できますが、実際活用しきれていないという人も。ミライロIDはマップから使える場所を見つける事ができるので、利用できる場所がとてもわかりやすいです。紙やカードタイプに比べて割引やサポートの活用のしやすさがアップします。
ミライロIDを利用するデメリット
利用時に障害者手帳と気づいてもらえない場合がある
ミライロIDはまだ新しいアプリのため、利用可能事業所でも対応する方によってはアプリを画像の写真と間違えて「使えない」と言われてしまうケースがあります。
障害者手帳の登録や管理に制限がある
現段階では、1つのアプリに1つのアカウント、1名分の障害者手帳しか登録できないなどの登録や利用に制限があります。 - 最後にミライロIDが使える場所について
- ミライロIDは全国の約4,000箇所で利用が可能です。電車やバス、タクシーなどの公共交通機関はもちろん、水族館や動物園、美術館でも利用ができます。マイナポータルの連携をしていないと使える場所が限られてしまう事があるので要注意です。
使える場所を調べたい時は、アプリのマップ機能から近くで使える場所を探すか、以下のサイトから検索できます。
ここから
ミライロIDを使っておでかけをスムーズに
ミライロIDを使う事でおでかけをお得に、スムーズにしやすくなります。普段出かけにくいな、と思っている人もおでかけによく行く人も、ぜひ試してみてくださいね。
(事務局長 小林誠)
山視協だより 令和7年1月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400-0005 山梨県甲府市北新1-2-12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 埜村 和美
編集責任者 事務局長 小林 誠
電話 055-252-0100
FAX 055-251-3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
先頭に戻る
目次へ
過去の情報はこちらから