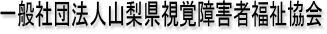山視協だより 令和7年2月号
第134号 令和7年2月14日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
| 行事報告 | |
|---|---|
| 第59回関東ブロック協議会茨城大会報告 | ・・・・・3 |
| 生活分科会報告 | ・・・・・3 |
| バリアフリー分科会報告 | ・・・・・4 |
| 職業分科会報告 | ・・・・・6 |
| 青年分科会報告 | ・・・・・8 |
| 女性分科会報告 | ・・・・・8 |
| R6第2回弱視部会、意見交換会報告 | ・・・・・9 |
| 今後の予定 | |
| 定期総会開催のお知らせ | ・・・・・9 |
| 全国視覚障害者福祉大会(千葉大会)参加者募集 | ・・・・・10 |
| 支部だより | |
| 富士河口湖支部 | ・・・・・10 |
| 事務局からのお知らせ | |
| 山視協70周年記念誌原稿募集 | ・・・・・11 |
| 県立中央病院の北側の歩道の改修工事について | ・・・・・11 |
| 山梨総合研究所フォーラムのお知らせ | ・・・・・12 |
| 忘れ物のお知らせ・バリアフリー図書 | ・・・・・12 |
| 編集後記 | ・・・・・13 |
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
行事報告
第59回関東ブロック協議会茨城大会報告
先頭に戻る
目次へ
会長 埜村和美
標記大会は1月18日(土)と19日(日)の両日、水戸市のホテルレイクビュー水戸を会場に開催され、本会からは付き添いを含む10名が出席しました。
第1日目は13時より記念式典続く基調講演では、宇野和博氏(筑波大学附属視覚特別支援学校教諭)による、演題「読書バリアフリーのこれまでとこれから」がありました。その後参加者は5つの分科会に分かれ、活発な審議や講演会がおこなわれました。そして団体長会議を経て懇親会が開催され、1日目を終了しました。2日目は全体会議が開催され、日視連会長挨拶に続き関東ブロック協議会事業報告がありました。そして前日におこなわれた分科会の結果が報告され、これにより千葉県の全国大会への提出議題が発表され、承認されました。そして大会宣言(案)と大会要望(案)が朗読され、拍手をもって採択されました。最後に次期開催団体栃木県から案内があり、全日程を終了しました。なお各分科会報告は、担当者がおこないます。
生活分科会報告
先頭に戻る
目次へ
埜村和美
生活分科会は、関東ブロック協議会長の鈴木孝幸氏を助言者に12団体からの提出議題について審議されました。12議題のうち7団体が、日常生活用具の給付基準額の引き上げに関するもので、日常生活用具の高騰で負担額の増加に苦しむ会員の生の声を感じました。地域間格差も問題とされる中、時間をかけての審議がなされました。提案議題中タブレットを日常生活用具にとの要望に対し助言者から一般の人も使用する機器なので、それは認められないとの回答でした。
次に同行援護事業所の従業員の増加と報酬単価の引き上げにより、安定した利用環境の確保についての要望は、本県からも提出された議題で、「ガイドヘルパーの日」も制定された今、引き続き力を入れていくべきとの意見で一致しました。
また医療機関でマイナ保険証を使用する際の視覚障がい者でも使用可能な体制作りや人的配慮の確保に対する要望など、進むデジタル化の昨今、速い対応が望まれます。これらの提出議題の審議の結果、全国大会への提出議題としては、「日常生活用具の給付基準額の上限額や給付品目については日視連がリストを作ってアップし、各団体に知らしめること」で承認されました。
バリアフリー分科会報告
先頭に戻る
目次へ
小田切浩子
本会からは角田貴弘理事と小田切が出席しました。座長は茨城県の森住純一氏、副座長は栃木県の兼目ちえ子氏、助言者は日視連弱視部会部会長の神田信氏、参加団体11団体でした。
視覚障がい者にとっての大きなバリアは情報取得と移動です。各団体から提出された11議題を情報と移動に分けてそれぞれ多数決で1議題ずつ選び最終的に1議題に絞り全国大会に提出されます。
多数決の結果茨城県の議題、交差点での視覚障がい者の安全な横断を確保するため、音響式信号機の増設を強く求める。特に近年増加の歩車分離式信号機については音響装置の併設は必須として取り組むこと。また、夜間・早朝の音響を停止していることについても、代替策を強く求める。この議題を全国大会に提出することが決定しました。
提案理由は歩車分離式信号機は、目前の車が停止しても歩行者用信号が青になったわけではないので、車の走行音だけでは視覚障がい者には判断できない。横断の安全を確保するためには歩車分離式と併せて音響式信号機の設置が必須と考える。また、せっかく設置してある音響式信号機が通勤時間帯に止められているのも視覚障がい者の安全確保が守られておらず改善が必要と思われるため。
私の生活圏内には歩車分離式はありませんが音が出ないととても危険であることは容易に想像がつきます。スマホのアプリで信号の色を認識するものもありますが、誰もが使えるわけではないし、音響式信号に比べると安全面で不安も残ります。信号の色を認識するためには音声だけでなく、振動で伝えるものも開発、普及してもらいたいと思いました。
ちなみに情報分野からは、川崎市の議題が選ばれました。スマートフォンなどで使用されるアプリは、スクリーンリーダーにより視覚障がい者も容易に利用できることを想定してアプリの開発・普及を進めることです。
提案理由は、スマートフォン等で使用されるアプリは、利便性が高く、普及が進んでいるが、視覚障がい当事者の利用が想定されていないためすべての機能を視覚障がい者が使用できないアプリも多い。アプリ開発にはユニバーサルな対応が必要であるためです。
本県からの議題はテレビ放送において、緊急放送の字幕の音声化、並びに表示の拡大化を早期実現することです。
提案理由は令和6年度も災害が多く、テレビでニュース速報の音は聞こえるが文字で表示されるのみで何が起きているのか、起こるのかが分からないためです。
栃木県でも同じような議題でしたが残念ながら全国大会提出議題には選ばれませんでした。会場内からの意見として、合理的配慮の観点からも実現に向けて声を上げ続けていくべきだ。団体として要望するだけでなく、個人的にも放送局のカスタマーセンターに要望したらどうか。文字の拡大化については、受像機メーカーへ要望する方が良いのではないかとの意見が出ました。緊急放送の字幕音声化は大切なことなので、他団体から全国大会の議案として上がることを期待しています。
職業分科会
先頭に戻る
目次へ
名取利一
職業分科会は座長に茨城県の稲田氏、副座長に栃木県の加藤氏、助言者として日視連の竹下会長、参加者は35名(ガイドヘルパーも含む)にて話し合われました。
議題としては10題の議案が出され、雇用関係・職域強化・就労支援・その他の4つに大きく分けられ検討されることとなりました。初めに雇用関係に関し、障害者雇用促進法により障がい者の雇用率は向上しつつあるが、あはき業を含めた視覚障がい者の雇用促進を促すため職域の拡大・行政施設や民間企業等への雇用促進、支援に関する議題が栃木県・横浜市から提案されました。
次に、職域強化では、視覚障がい者の職域を守るため、公共機関・民間企業等へのヘルスキーパーの雇用を積極的に働きかけることを要望すること、などの議題が群馬県・千葉県・神奈川県・山梨県から提案されました。この件に対し、給与に関する情報であるが、一口に同じヘルスキーパーと言っても雇用体系によって違いが生じ、特にA型作業所で雇用された場合、たとえ国家免許の保有者であっても、給与が低額で雇用されるケースがあるという情報がありました。また、正規のヘルスキーパーとして雇用された場合は、施術だけでなく産業カウンセラー的役割も果たせるよう心掛けても良いのではないかと言うアドバイスがありました。
次に、就労支援においては、視覚障がい者の就労支援、復職を目的とした訓練施設の充実、民間企業・公共機関等で働く視覚障がい者に対する職場介助者の充実、並びに人材確保を充実させること、などが千葉市・東京都・茨城県から提案されました。
近年のIT化により事務職なども増えているが、職場環境が全ての職場で充実している状況とは言えない。雇用施策の連携により、重度障害者等就労支援特別事業を実施し、就労訓練・職場環境の整備・通勤や営業活動などの安全確保など、視覚障がい者が働きやすい環境づくりが議題の主な内容でした。
最後に、視覚障がい者の自営業者がキャッシュレスによる支払を受けるにあたり、音声などによる扱いやすい端末を開発することが川崎市から提案されました。電子決済化が身近となり、キャッシュレスによる支払いを求める方が多くなっていることを踏まえ、視覚障がい者が対応しやすい端末の開発を求めたいという要望でした。
これで全ての議題が審議され、結果、就労支援で検討された千葉市・東京都・茨城県から出された議題の内容がほぼ同じなので、執行部で内容を取りまとめ関東ブロックの提案議題とすることが承認されました。
青年分科会報告
先頭に戻る
目次へ
小林 誠
青年分科会は、講演者にヴァイオリン・ヴィオラ奏者、作編曲家の穴澤雄介氏を迎え、「視覚障害を強みに変えるアイディアと生き方」という演題でお話ししていただきました。
穴澤さんは、視覚障がいがあるマイナスイメージの中で、それを受け入れて、「視覚障がいがあるからこそ、他の感覚を利用して、どのようなことができるのかを考えることが大切だ」と述べられています。穴澤氏のヴァイオリン奏者としての人生の中で、最初は、片っ端から音楽業者に連絡を取ったが、実績がないと言われ断られることが多かった。そこから発想を転換し、老人ホーム・病院・保育園などを回って演奏活動をつづけ、実績を上げて少しづつ仕事がもらえるようになってきた。そして、小さな優勝経験を積み上げて名前を憶えていただけるようになり、今に至る。と話してくれました。
後半の40分間は、穴澤氏のヴァイオリン演奏を披露していただき、充実した時間を過ごすことができました。
女性分科会報告
先頭に戻る
目次へ
小笠原恭子
「災害ボランティア活動をしていて気づいたこと」という演題で、元ボーイスカウト隊長の鷹崎繁幸氏の講演がありました。東日本大震災以来、日本各地の災害ボランティアの経験をふまえ、災害現場の実情や災害別の状況をお話しいただきました。
避難所はとにかく混雑しているので自分の障がいの状態を管理者に伝え、目が不自由であれば壁側がいいとか入口に近い方がいいとか希望を伝える必要があるというアドバイスがありました。
特に強調されていたのはトイレが困るということでした。実際に非常用トイレが会場に回されましたが、パッケージの上からではどういうものが入っているのか、どう使うのか分かりませんでした。
本会でも防災グッズの体験会ができるといいなと思いました。
R6第2回弱視部会、意見交換会報告
先頭に戻る
目次へ
吉村圭子
昨年12月18日(水)18時30分から弱視部会 第6回オンライン意見交換会が開催されました。テーマは「弱視者(ロービジョン)の歩行」で、以前の意見交換会で提出された意見についてまとめた資料をもとに進行しました。資料は歩行での困りごと、工夫していることが掲載されています。(資料については山視協ホームページに掲載しました。)
色々な意見や感想などが出ましたが、中でも「やってもらったことにお礼を言うことが大切」と言う意見が印象に残りました。確かに、さまざまな困りごとに対し要望を出して、それが実現された時に「合理的配慮」で片付けず、素直にお礼を言うことで、相手との関係性がうまくいくことはありそうに思い、なるほどと思いました。
皆さんが調査に行かれたり、日頃遭遇している横断歩道、点字ブロック、信号、案内表示などの困りごと、反対に助かっていることなどを共有することで、工夫できることがあると感じました。
今後の予定
定期総会開催のお知らせ
先頭に戻る
目次へ
令和7年度の定期総会を次の日程にて開催いたします。
山視協の今後を左右する議題がありますので、より多くの会員の出席をお願いいたします。
- 日時 4月20日(日) 午前10時から12時
会場 やまなし地域づくり交流センター4階大会議室 - 詳しい内容につきましては、3月号にてお知らせします。
全国視覚障害者福祉大会(千葉大会)参加者募集
先頭に戻る
目次へ
来る5月25・26日に第78回全国視覚障害者福祉大会が千葉県にて開催されます。地元、関東地区で開催するため、多くの会員の出席をお願いしたいと関東ブロック協議会より連絡をいただいています。
- 日時 5月25日(日)・26日(月)
会場 千葉市TKP東京ベイ幕張ホール
申し込み締め切り 2月28日(金) - 詳しい内容につきましては、事務局までお願いします。
電話 055-252-0100
皆様のご参加をお待ちしています。
支部だより
富士河口湖支部
先頭に戻る
目次へ
支部長 近藤とみ子
円安効果でこの地域も外人で溢れています。ホテルのお客様のマッサージをさせて頂いているのですが、今の主流は外国人です。先日あるホテルで、フランスから単独で来た32歳女性のお客様と知り合いました。35分間の施術の中で、日本の文化を学びに来たという度胸の良さに頭が上がりませんでした。お金を頂き、サンキューとバイバイを繰り返し部屋を出るとき、キャラメルを一粒手に握らせてくれました。心があったかくなりました。この仕事でなければ感じられない一期一会でした。
事務局からのお知らせ
山視協70周年記念誌原稿募集
先頭に戻る
目次へ
記念誌担当 小田切浩子
来年度は本会創立70周年記念事業を行います。その一環として記念誌の発刊を予定しています。そこで会員の皆様から記念誌に掲載する原稿を募集いたします。テーマは特に決めていないです。会のこと、日常生活のこと、文芸、何でも良いです。原稿をお寄せください。原稿締め切りは3月末とさせていただきます。
郵送の場合は本会事務局 〒400-0005 甲府市北新1-2-12 福祉プラザ1階 山梨県視覚障がい者福祉協会までお願い致します。
メールの場合はkinenshi70@yamashikyo.sakura.ne.jpまでお願いします。
皆様の原稿をお待ちしています。
県立中央病院の北側の歩道の改修工事について
先頭に戻る
目次へ
工事期間は2月6日から3週間程度ということです。工事区間はケヤキ通り西側を右折し、音響式信号機がある交差点から、荒川の東側道路と交差する交差点の信号機までです。工事は夜間に行われるということで、日中、歩道を歩くことはできます。アスファルトを全て取り除くということなので、車道と歩道の境、歩道と病院敷地内との境、また、歩道上も工事区間との境に、少なくとも5センチ程度の段差が出てしまうので、この歩道を利用する際は注意してくださいと言うことでした。
特に注意していただきたい箇所は、病院入り口の東から約10メートル位に、北側に渡る横断歩道があるのですが、段差がさらに大きくなる可能性があるので、特に注意してください。
公益財団法人山梨総合研究所フォーラムのお知らせ
先頭に戻る
目次へ
- データ×フカボリ=シアワセ? 新たな山梨の見つけ方
日時 2月26日(水)13時30分~16時30分
場所 やまなし地域づくり交流センター4階大会議室
定員 30名
申込・お問合せ 055-221-1020(佐藤・山本・在原様)
プログラム
1.データから見える景色とは? - ・幸せは何で作られているの? ・バスに乗ってどこにいく?
・幸せな働き方への近道は?
・若者のメンタル維持に欠かせないものは? - 2.「フカボリの先にあるものは?」
2つのテーマに分かれて、ディスカッション - ・視覚障がい者のこと、知っていますか?
・子どもの貧困って、お金だけ?
忘れ物のお知らせ・図書紹介(バリアフリー図書)
先頭に戻る
目次へ
体育文化部研修の際、2号車に水筒の忘れ物がありました。ご案内が遅くなりましたが事務局でお預かりしています。お心当たりの方は事務局までお願いします。
『障害者と健常者がともに楽しむ旅行』発行 社会福祉法人桜雲会
点字・墨字合本・全1巻 ご覧になりたい方は事務局までどうぞ。
編集後記
先頭に戻る
目次へ
今年に入り、早いもので2月の半ばを迎えています。来月には、桜の花も咲き乱れ、旅行シーズンを迎えます。今年もJRを始め各鉄道会社がこの春のダイヤ改正を発表しています。私たちに身近な中央線もいくつか改正がありますので、お知らせします。
① 平日に甲府駅5時台発の上り「かいじ」が登場。東京駅に8時前に到着。
この臨時特急は、山梨エリアから、東京方面への通勤・通学の利便性を図ることを目的にダイヤ改正が行われます。甲府を5時40分に出発し、東京には、7時45分に到着します。途中停車駅は、石和温泉、山梨市、塩山、大月、八王子、立川、新宿に停車します。
② 松本と東京方面を結ぶ特急あずさの下りについて、午後5時以降の時間帯は、始発を新宿から東京に切り替える。
あずさは1日に上下各16本が運行。東京方面からの下りは現在、午後4時45分発の41号が唯一の東京発。残りは新宿発14本、千葉発1本。改正で41号に続く45号、49号、53号、55号と夕方以降の全4本の始発駅が新宿から東京に変わる。これにより、各新幹線からの乗り換えがスムーズになるという。
③ 上下4本の車両編成を9両から12両にする。
車両編成が増えるのは、下りが21号(新宿正午発)と45号、上りが12号(松本午前8時10分発)と42号(同午後3時10分発)。改正により、12両編成の本数は12から16に増え、9両編成と同数となる。
この3月のダイヤ改正で、中央線特急の利便性がさらに良くなりそうですね。
(事務局長 小林誠)
山視協だより 令和7年2月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400-0005 山梨県甲府市北新1-2-12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 埜村 和美
編集責任者 事務局長 小林 誠
電話 055-252-0100
FAX 055-251-3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
先頭に戻る
目次へ
過去の情報はこちらから