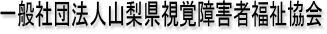山視協だより 令和7年12月号
第144号 令和7年12月15日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
| 巻頭言 | |
|---|---|
| 視覚障がい者が日常生活で抱えている困りごと | ・・・・・2 |
| 行事報告 | |
| 山視福協創立70周年記念大会に参加して | ・・・・・3 |
| ふれあいマーケットに参加して | ・・・・・5 |
| 支部だより | |
| 富士吉田支部 | ・・・・・6 |
| 事務局より | |
| 令和7年度第1回人権啓発講師養成研修会の動画公開について | ・・・・・7 |
| トピックス | |
| おめでとうございます! | ・・・・・8 |
| 編集後記 | ・・・・・8 |
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
巻頭言
視覚障がい者が日常生活で抱えている困りごと
先頭に戻る
目次へ
会長 小林誠
先月行いました「創立70周年記念大会」には、多くの方のご出席をいただき、まことにありがとうございました。本会としてもこの大会を新たなるスタートとして視覚障がい者のより一層の福祉の向上に努めてまいる所存でございます。
さて、大会内でも視覚障がい者の買い物事情についてシンポジウムを行いましたが、昨年4月の「改正障害者差別解消法」施行以来、視覚障がい者が困難を抱える実例にどのようなものがあるのか内閣府資料から紹介します。
- 1 代筆・代読(情報・コミュニケーション)関係
- 事業者に代筆・代読を依頼しても、対応してもらえないことに困っている視覚障がい者が多く存在する。長時間にわたって事業者側に依頼しても断られてしまい、日視連が設置している総合相談室に相談する視覚障がい者は多い。相談の相手方となる事業者として最も多いのは金融機関であるが、宿泊施設、医療機関のほか、公的機関等も多い。
なお、マイナ保険証が運用されるようになり、医療機関に関する相談が増加している。例えば、マイナ保険証の読み取りが上手くできないため、医療機関のスタッフに読み取りの支援等を依頼するが、断られる事例がある。中には「もう、この病院には来ないでくれ」と言われた事例も報告されている。
また、医療機関においては、視覚障がい者が手術に関する同意書を書けない、または代筆できる家族を呼べない場合もある。このような場合には、本人の意思を確 認した上で、代筆・代読が行われる必要がある。
- 2 移動関係
- 視覚障がい者が買物をするため、店舗スタッフに案内を依頼することがある。このような場合、視覚障がい者が店舗側に事前に相談を行ったり、他の利用者の少ない時間帯を選んで案内を依頼する等の工夫をしても、店舗側から案内を断られることが多い。
また、視覚障がい者が鉄道事業者に対して案内を依頼することもある。このような場合、鉄道事業者からは、例えば、最低でも30分前に駅に来て依頼することを求められることや、ターミナル駅の場合には、別の鉄道事業者への引き継ぎを断られることがある。 - 3 同行援護関係
- 同行援護事業においては、利用者である視覚障がい者が同行援護従業者に対して、サービスの範囲を超えた要求を行う事例や、強い語調で自己の要求に沿うよう求める事例が報告されている。カスタマーハラスメントに関する指針が策定されることにより、利用者である障がい者にも、節度ある姿勢でサービスを利用することが求められるケースもある。
本会員の皆さんにも多くの実例が存在していることでしょう。そんなフリートークの機会を近々持ちたいと考えています。ご意見やご要望等、お寄せいただければ幸いです。
行事報告
山視福協 創立70周年記念大会に参加して
先頭に戻る
目次へ
返田順子
去る11月9日(日)、100名を超える参加者のもと、山視福協創立70周年記念大会がベルクラシック甲府にて開催されました。
第1部 記念講演会では、日本視覚障害者団体連合竹下会長をお迎えし、「地方における視覚障がい者団体の課題と展望」と題し、貴重なお話を聞くことができました。全国的に会員数が減ってきている中、仲間同士悩みを打ち明け合い、共有してよりよい生活が送れるよう、仲間の輪を広げることの大切さを実感した講演でした。
第2部 記念式典では、主催者あいさつに続き、県知事感謝状並びに山視福協会長感謝状が、功績のあった各団体と個人に贈呈されました。来賓の祝辞の後、シンポジウムが行われました。視覚障がい者の買い物事情をテーマに、3人のパネラーと司会者により、買い物をめぐる困りごとについて意見交換がされ、みなさんそれぞれに工夫している様子がうかがえました。なかでも、レジが無人化されている店が多くなり、戸惑っていること、店員を見つけることが困難なこと、商品の文字が見にくいなど、より快適に買い物ができるよう、店側に働き掛けていく必要性を確認したシンポジウムでした。
続いて、2階から3階に移動しての第3部記念祝賀会では、主催者あいさつ、来賓あいさつ、乾杯と進み、おいしい料理をいただきながら、参加者の自己紹介と続きました。久しぶりに会う会員も多く、あちこちのテーブルから楽しそうな話し声や笑い声が聞こえていました。アトラクションでは、10年振り返りクイズで各テーブルごとに答えを相談しながら、代表者が腕を使って大きなマルを出したり、バツを出したりして、和気あいあいのうち、「次は80周年を目指して」を合言葉に
閉会となりました。
この会を成功させるため、準備に携わってくださった関係者のみなさま、本当にありがとうございました。なお、記念誌「あゆみ」もできましたので、会員のみなさま、じっくり味わいながらお読みください。
ふれあいマーケットに参加して
先頭に戻る
目次へ
就労生活部長 酒井弘充
就労生活部では、平成27年より県民の日記念行事のひとつである「ふれあいマーケット」に参加してまいりました。新型コロナウイルス感染症の影響により、行事そのものの中止や、当会の参加見送りなどがあり、4年間の中断期間を経ましたが、本年度も継続して参加することができましたので、ここにご報告いたします。
今回の「マッサージフェスタ」は、11月16日(日)に小瀬スポーツ公園で開催され、ブースは、テント1張に長机とパイプ椅子を設置した簡素な構成でしたが、会場のほぼ中央で大きな通りが交差する非常に良い場所に設けることができました。また、看板には、70周年記念品として配布されたエコバッグに描かれている盲導犬と白杖のイラストを掲示し、視覚障害者福祉への理解促進にも努めました。
当日は、就労生活部員6名に加え、「山視協だより」で募集した会員5名の施術者にご協力いただきました。さらに、山障協の赤野様、ならびに「わの会」から2名のご協力も得て、午前10時から午後3時までの間に、延べ105名の方に施術を行いました。
施術は、来場者の皆さまに「本物のマッサージ」を知っていただくことを目的として実施しました。お一人あたり約15分の施術時間の中で、以下のような内容について必ずお話しするように心がけました。
今年度も中止となった「鍼灸の日」に駅前で配布していたチラシをリニューアルし、表面には「無資格者にご注意を!」という注意喚起の内容を、
裏面には県内5つの保健所管内に届け出のある施術所一覧のホームページにリンクするQRコードを掲載しました。このチラシをお渡ししながら、内容について丁寧にご説明しました。このような1対1の対話は、施術時間内に無理なく行うことができ、非常に効果的であったと感じています。施術を受けた多くの方が、これまで体験したものとは明らかに異なると気づかれ、感嘆の声を上げてくださいました。
また、「昨年度の施術がとても良かったので、今年も来ました。」という声や、「このブースを目当てに県民の日の行事に来ました。」という方も多数いらっしゃいました。
このようなことからも、「マッサージフェスタ」は「本物のマッサージを県民の皆さまに広く知っていただく機会とする」という当初の目的を、十分に果たすことができたと強く実感しております。なお、今回の施術には料金を設定せず、山視福協の活動援助を目的とした募金箱を設置させていただきました。その結果、昨年を上回る34,706円という尊いご寄付をお預かりいたしました。この寄付金は、本会の雑収入として処理させていただきます。
支部だより
富士吉田市視覚障害者協会
先頭に戻る
目次へ
会長 荻窪たき子
こんにちは。暦は早くも師走となり、何かと気忙しい季節の中ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。時の経つのが速すぎて、私は目が回るような焦りすら感じるほどです。
さて、11月9日には山視福協創立70周年記念大会が盛大に挙行されました。長きにわたり、本県の視覚障がい者への福祉の向上にご尽力いただいていることに
心より感謝を申し上げます。大変おめでとうございました。
富士吉田支部の会員さん方は、国中での事業等にはなかなか参加できないこともあり、少しでも移動のハードルを下げるべく、今回は貸切バスを利用し、今年度の社会学級として皆さんと一緒に出席させていただきました。
日視連の竹下会長のご講演を拝聴し、大きな団体でも小さな団体でも同じ苦悩があることなど同感した次第です。懇親会でも、とてもおいしくて食べやすく工夫されたお料理の数々に、おなかいっぱい幸せ気分で帰路につきました。
昨年度を振り返ってみますと、本会も創立60周年を迎え、12月には大勢のご来賓にもご出席を賜り、また会員・賛助会員・関係各位のご協力をいただき、無事に記念式典を開催することができました。
他にも、6月の定期総会、8月の社会学級でレリーフアート作り、10月はパラスポーツ体験の研修会を実施しました。残念ながら3月に予定していたパン作りの料理教室は雪のために中止となってしまいました。
本年度も、同じく6月に定期総会、7月には山障協主催の障害者文化展に出品すべく、講師の先生を迎え短歌教室を実施しました。この後も、12月に会員からの要望のあったカラオケボックスでの忘年会、そして3月には昨年度のリベンジのパン作り教室を予定しております。
その他には例年と同様に、行政や各関係機関への要望活動や協力体制をとり、私たち視覚障害者の社会参加や生活の質の向上を目指すとともに、公共交通の脆弱な郡内だからこその移動の問題解決、災害弱者としての防災の課題など当事者の声を届けることや、深刻な会員減少の問題などに対しても、役員一同で積極的に取り組んでいきたいと考えております。
それでは、少し早いですが皆さんどうぞよいお年をお迎えください!
事務局より
令和7年度第1回人権啓発講師養成研修会の動画公開について
先頭に戻る
目次へ
動画には人権啓発に関する講師を行う上で基礎的な内容、参考になる内容等が含まれており、日視連のYouTubeチャンネルで公開されています。
なお、第2回の研修会は令和8年1月12日(月・祝)13時から16時に開催されます。参加希望の方は事務局までご連絡ください。
URL:https://www.youtube.com/watch?v=AUSuMwU-Z5E
または、次のリンク先よりどうぞ
ユーチューブへのリンクはこちらから
開催内容
マニュアル・テキストの説明
令和6年度アンケートの説明
講師の体験談の報告
意見交換
トピックス
おめでとうございます
先頭に戻る
目次へ
前会長の埜村和美さんが令和7年度山梨県県政功績者表彰を受賞されました。
令和7年度障害者援護功労者等知事表彰において
自立更生者として 山内美和さん
特別表彰として パラ陸上競技で活躍されている白濱顕子さんとそのガイドランナーの由井玄太さんが受賞されました。
益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
編集後記
先頭に戻る
目次へ
気が付けば2025年も残りわずかとなりました。今年のメインイベントとであ創立70周年記念大会も無事終わり、安堵しているところです。
記念誌「あゆみ」と一緒に70周年の記念品として作成した山視協オリジナルのエコバッグがお手元に届いていると思います。このエコバッグは紺色で、真ん中にハーネスを付けてお座りした盲導犬が座っていてその後ろに富士山、犬の右側にブドウのストラップがぶら下がっている白杖が描かれているイラストがあります。たたんで丸めたときに持ち手のところについている輪っかで止められるようになっていて、マークがかわいいと評判です。ご愛用ください。
(事務局長 小笠原恭子)
山視協だより 令和7年12月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400−0005 山梨県甲府市北新1−2−12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 小林 誠
編集責任者 事務局長 小笠原恭子
電話 055−252−0100
FAX 055−251−3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
先頭に戻る
目次へ
過去の情報はこちらから